微生物インタラクション研究室の渡辺大輔准教授が日本醸造学会の「日本醸造学会奨励賞」を受賞
微生物インタラクション研究室の渡辺大輔准教授が日本醸造学会の「日本醸造学会奨励賞」を受賞しました(2025年10月8日)。
受賞のコメント
このような名誉ある賞を賜りまして、これまでご指導いただいた先生方、共同研究でお世話になった産官学の皆様方、研究を支えてくれた学生・スタッフの皆様方に心より御礼申し上げます。発酵・醸造微生物の一研究者として、先人たちの知恵に学び今の時代を生きる自分に何ができるかと必死に取り組んでいるつもりですが、何かを成し遂げたという実感はありません。まだまだ未熟でこれからだと思っていて、そんな私への激励の意をこめて賞を授けてくださったのだと理解しております。これを一層の励みとして、次世代の発酵・醸造微生物研究者にバトンをつなげられるような研究、そしてこの分野のわくわくする魅力を発信できるような研究に、微力ながら今後も取り組んでまいりたいと思います。

受賞研究課題名
醸造微生物の代謝デザインと生態系ダイナミクスに関する研究
受賞内容
酵母のアルコール発酵力は人為的な制御が困難とされてきたが、発酵力に優れた清酒酵母の研究を端緒として、アルコール発酵の主要な阻害因子であるRim15pプロテインキナーゼを見出した。真核生物に保存されたTORC1-Rim15p-PP2AB55δ経路が、転写因子Msn2/4pを介した遺伝子発現を通じてアルコール発酵を制御するシグナル伝達の全体像を解明するに至った。その下流では、酵母細胞壁の主要構成成分である1,3-β-グルカンの合成とアルコール発酵との間にトレードオフ関係が存在することを明らかにし、細胞壁合成阻害剤を活用した遺伝子組換えを伴わない発酵力改変育種法を提唱した。酵母のアルコール発酵デザイン技術は社会実装の観点からは依然開発途上であるが、実現可能性を具体的に示した点に本研究の意義がある。これからの発酵業においてその応用展開が期待される。
上記の研究に並行して、伝統的発酵食品における微生物相互作用や生態系構造の解明にも進展が見られた。清酒の伝統的製法である生酛造りでは、乳酸菌の生育に導かれるように酵母が増殖し酒母が形成される。乳酸菌は酵母の転写コリプレッサーCyc8pを介した遺伝子発現抑制を解除することでアルコール発酵を一時的に阻害し、両者の共生的関係を成立させることを明らかにした。さらに近年は、清酒の副産物である酒粕を再利用したサステナブルフードの先駆けともいえる奈良漬に注目し、伝統的製法下でのみ生育する好エタノール性乳酸菌が乳酸発酵に関与していることを発見した。これらの成果は、醸造微生物が発酵食品の製造環境に適応し機能を発揮するための根源的原理を解き明かすことに繋がる。
発酵食品の中には、いまだ微生物群の全容すら明らかでないものや、科学的な裏付けのないまま経験的に継承されてきた技術も見られる。こうした伝統技術に含まれる暗黙知を、ゲノム情報・遺伝子発現・代謝プロファイルなど多層的データから解読することにより、発酵食品の生産安定化と高付加価値化に資する科学的基盤の構築を目指している。以上のような知見は、醸造微生物研究の次世代展開において中核的な役割を果たすものである。
授賞団体名
関連資料
【原著論文】
Watanabe et al., J. Biosci. Bioeng., 126, 624 (2018)
Watanabe et al., Appl. Environ. Microbiol., 85, e02083-18 (2019)
Watanabe and Hashimoto, Sci. Rep., 13, 9279 (2023)
Watanabe et al., NPJ Sci. Food, 7, 37 (2023)
Watanabe et al., Int. J. Mol. Sci., 25, 304 (2024)
吉岡求, 渡辺大輔, 日本醸造協会誌, 119, 338 (2024)
【微生物インタラクション研究室】
研究室紹介ページ:https://bsw3.naist.jp/courses/courses313.html
研究室ホームページ:https://bsw3.naist.jp/microbial_interaction/
(2025年10月14日掲載)
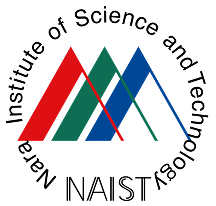 奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学